――運営、正気か?
この一言から始まる物語が、こんなにも自由で、こんなにも笑えて、そしてこんなにも痛快だとは、誰が想像しただろう。
『デスゲームに巻き込まれた山本さん、気ままにゲームバランスを崩壊させる』は、カクヨムコン8でエンタメ総合部門大賞&ComicWalker漫画賞をW受賞した、今もっとも注目されるVRMMO系ライトノベルだ。
タイトルの通り「デスゲームに巻き込まれる」設定ながら、主人公・山本凛花(ヤマモトさん)は悲壮感ゼロ。むしろ、圧倒的にマイペース。
彼女が手にしたユニークスキル【バランス】――それは「全てにおいてバランスを取る」という、聞こえは地味なのに、結果としてゲーム世界の根幹を崩壊させていくとんでもない能力だった。
普通のデスゲーム小説が“命の駆け引き”を描くなら、本作は“世界そのものを遊ぶ”物語。 シリアスさとユーモアの境界線を軽やかに踏み越えながら、読者に笑いとカタルシスを同時に叩き込んでくる。
そして何より――この作品が持つ最大の魅力は、山本さん自身の“等身大のゲーム感覚”にある。 彼女は特別な英雄ではない。ただのゲーマーであり、仕事帰りにエナドリを片手にプレイする絵師。 だが、そんな現実感を持つキャラだからこそ、VR世界での自由奔放な活躍がとんでもなく輝く。
「のんびり生きるはずが、なぜか世界を壊してしまう」――そんな逆転構造に、読者はすぐ夢中になるだろう。
この記事では、公式あらすじと第10話までの内容をもとに、ネタバレを最小限に抑えつつ、“この作品を今読む理由”を解説していく。
VRゲーム×デスゲーム×チートスキル×コメディ――この4要素をここまで自然に融合させた小説は、今のWeb小説界でもそう多くはない。 読後、あなたもきっと「運営、正気か?」と笑いながら呟いてしまうはずだ。

『デスゲームに巻き込まれた山本さん』とは?(カクヨム発・W受賞の超話題作)
まず、この作品がどんな立ち位置にあるのかを整理しておこう。
『デスゲームに巻き込まれた山本さん、気ままにゲームバランスを崩壊させる』は、カクヨムにて連載中のVRMMORPG系ライトノベル。
作者はぽち氏。
カクヨムコン8(第8回カクヨムWeb小説コンテスト)において、エンタメ総合部門大賞およびComicWalker漫画賞のW受賞を果たした実績を持つ。
さらに、角川スニーカー文庫より書籍第1〜4巻が刊行中(2025年10月時点)。
つまり、“Web発→商業化→コミカライズ”の三段跳びを成功させた、王道の成功モデル作品なのだ。
だが、その中身は一筋縄ではいかない。
タイトルの印象から「命懸けのサバイバル系」を想像する読者も多いが、実際は死と笑いのバランスが見事に共存した「崩壊系デスゲーム・コメディ」である。
そのギャップこそが、本作最大の魅力だ。
VRMMORPG『Life is Adventure』という舞台
物語の舞台は、超体感型VRMMORPG『Life is Adventure』(通称LIA)。
初回出荷十万本が即完売、体感レベルが“現実と変わらない”と評された次世代ゲームだ。
プレイヤーの五感を完全に再現し、食事・痛覚・匂いまでも再現するという仕様は、現代VR技術を極限まで拡張した設定となっている。
この設定はフィクションでありながら、実際のVR研究・触覚フィードバック技術(例:Meta QuestのHaptics研究など)にも通じる“リアリティの再構築”として説得力を持つ。
作中でも、現実に存在するMMORPG用語(チュートリアル、セーフティエリア、SP=スキルポイント、称号システムなど)が自然に組み込まれ、読者に「あるかもしれない世界」として機能する。
主人公・山本凛花――“バランス”を崩す天才
主人公の山本凛花(ヤマモトさん)は、現実では絵師として働く社会人ゲーマー。
初期設定からして異色だ。
多くの異世界/VRMMO作品が“学生”や“引きこもり”を主人公に据える中、山本さんは自立した社会人ゲーマーとして描かれる。
彼女の特徴は、「現実的すぎるノリ」と「理不尽を笑い飛ばす胆力」。
LIAへの当選に全力で歓喜し、仕事を一気に片付けて“廃プレイの準備をする”冒頭は、読者のゲーマー心を直撃する。
そして――いざゲーム開始。
彼女が選んだ種族は“ディラハン”(首なし騎士の妖精種)。
選んだ理由も「人間だとモテすぎて面倒だから」という、どうしようもなく人間くさい動機だ。
そして手に入れたユニークスキル【バランス】。
説明文は「全てにおいて、バランスが取られる」。
……それだけ。
しかしこのスキルこそが、物語の核となる。
ステータスを上げると全項目が連動して跳ね上がり、スキルを1つ取ると関連スキルまで自動で取得される。
その結果、山本さんはチュートリアル前にして“賢者クラスのオールマイティ”と化す。
まさに、ゲームバランス崩壊。
でも彼女は「まぁいいか」で済ませてしまう。
この致命的な異常を軽口で受け流すテンションが、本作のコメディ性を一気に高めている。
デスゲーム要素の“肩透かし”が生む新鮮さ
本作のもう一つの特徴は、“デスゲーム”という重い題材を、ほぼ真逆のトーンで描いている点だ。
通常、このジャンルでは「恐怖」「命懸け」「裏切り」が主軸になる。
だが『山本さん』では、プレイヤー同士の殺し合いよりも、山本さんがどう「自由に楽しむか」に焦点が置かれている。
彼女にとってデスゲームとは、命を賭ける場ではなく、「運営のバグを逆手に取って遊ぶ場」なのだ。
その結果、読者は“死”ではなく“生”――すなわち“遊びの快楽”を感じる。
この逆転構造が、デスゲームというジャンルの既成概念をひっくり返す。
“のんびり”と“殺伐”の共存がクセになる
ヤマモトさんのプレイスタイルは徹底してマイペース。
戦闘よりも錬金や鍛冶、鑑定などの生産スキルを優先し、馬車をカスタムして拠点化する。
デスゲームの真っ只中でクラフトに夢中――そのアンバランスさが読者の笑いを誘う。
しかも、この“のんびり”がただの癒やしでは終わらない。
彼女の【バランス】スキルが発動するたびに、世界の理がズレていく。
気づけば、彼女の存在そのものがゲーム全体の“システムバグ”になっているのだ。
それでも本人は気づかず、今日ものほほんとプレイを続ける。
この、笑えるのにどこか背筋が寒くなる感覚――まさに“デスゲーム×コメディ”という異種融合が生み出す中毒性だ。
第10話時点で見える物語の方向性
第10話までの構成で描かれるのは、“序章”にあたる部分。
ヤマモトさんがスキルの異常性に気づきつつも、それを“便利だからOK”と受け入れてしまう過程が中心となる。
プレイヤー仲間との出会い(フェアリードラゴンのタツなど)も始まり、世界の広がりを予感させる展開だ。
物語全体としては、“チートを持った普通の人間が、異常を日常として楽しむ”という構造に着地しつつある。
つまり、これは「最強主人公」ではなく、「最強を無自覚に遊ぶ主人公」の物語。
そのスタンスが、デスゲームというジャンルに新しい風を吹き込んでいる。
作品データ・出典
- 掲載サイト:カクヨム公式『デスゲームに巻き込まれた山本さん、気ままにゲームバランスを崩壊させる』作品ページ
- 作者:ぽち氏
- 受賞:カクヨムコン8 エンタメ総合部門大賞/ComicWalker漫画賞(W受賞)
- 書籍版:角川スニーカー文庫(第1〜4巻発売中/KADOKAWA公式書籍情報に準拠)
- 参照日:2025年10月8日
『デスゲームに巻き込まれた山本さん』感想と見どころ(崩壊を笑え!新世代バランス系ヒロインの魅力)
一読してまず驚くのは、この作品が「デスゲーム」なのに“救い”の気配を失っていないということだ。
むしろ、死が当たり前の空間の中で、“生きることを楽しむ人間”の姿を描いている。
それが山本さんであり、この作品の最大の美点である。
この記事では、第10話までを踏まえ、ネタバレを避けつつ、作品が読者を惹きつける三つの軸――「構造の面白さ」「キャラクター性」「読後感の余韻」――から魅力を掘り下げていく。
① バランスが壊れる快感──“チート”を笑いに昇華する設計力
ライトノベル読者にとって、“チート能力”はもはや見慣れた要素だ。
だが、本作のスキル【バランス】は、単なる“最強設定”では終わらない。
なぜなら、このスキルは「全ての数値が均等になる」という仕組み上、上げても下げてもゲーム全体を巻き込む“構造バグ”を内包しているからだ。
ステータスを上げれば、周囲の敵も一緒に強くなる。
ダメージを受ければ、味方までHPが減少する。
――つまり、「強くなること」がリスクになっている。
このパラドックスが最高に痛快なのだ。
山本さんはこの異常を「まぁ、バランス取れてるならいっか」と軽く流す。
普通の主人公なら絶望する場面で、彼女は笑って先に進む。
この軽妙なノリが、重くなりがちなデスゲームものを一気に“爽快系コメディ”に変えている。
読者としても「そんな調整ある!?」と突っ込みながら、気づけばページをめくる手が止まらなくなる。
② ヤマモトさんの“社会人感覚”が生むリアリティと安心感
彼女が他作品の主人公と一線を画すのは、その人生経験値にある。
多くのVRMMO系ライトノベルが“若者の成長”を主軸に置くのに対し、本作の主人公は「社会を知っている人間」だ。
仕事の愚痴を言い、コンビニ飯を愛し、睡眠時間を削って遊ぶ。
そのリアリティが、デスゲームという非現実を“自分ごと”として感じさせる。
彼女の軽口はただのギャグではなく、現実逃避でもない。
仕事や日常のストレスを知っているからこそ、「遊びの自由」が尊く見える。
その視点があるから、本作のユーモアは決して浮つかない。
読者は山本さんに「わかる、それ!」と共感し、そして「この人、やっぱり強いな」と憧れる。
現実の疲れを笑いに変える――そんな大人の余裕が、この作品を唯一無二にしている。
③ デスゲーム×コメディの融合が生む中毒性
この作品の構造的な面白さは、“恐怖”と“笑い”が同時に走ることだ。
世界観は確かに命懸け。
だが、山本さんは死を恐れず、むしろ「この仕様、ヤバくない?」とゲーム的に楽しむ。
通常、デスゲーム作品ではプレイヤー同士の殺し合いや心理戦が中心になる。
しかし本作では、その“恐怖の舞台”がエンタメ空間に変換されている。
システムエラーや運営の暴走すら、彼女にとっては“イベント”でしかない。
この感覚が、読者に強烈な快感を与える。
命の危険よりも、ゲームそのものを“遊び倒す”愉快さが前に出てくる。
そして、その明るさが逆に“世界の歪み”を際立たせる。
笑っているのに、背後にうっすら不穏な影が見える――。
この絶妙な緊張感が、まさに“崩壊コメディ”の真骨頂だ。
④ メタ構造と“プレイヤー視点”の妙
物語の随所で見られるのが、プレイヤー視点を活かしたメタ的ユーモアだ。
UIのエラー、システムのバグ、掲示板の反応……。
こうした“運営の都合”や“システムの裏側”をネタとして描く手法は、現代のオンライン文化を知っている読者にとって非常に刺さる。
しかも、作者・夏野すずね氏自身が実際にオンラインゲーム文化を深く理解しているため、描写が自然で嘘がない。
「こういうプレイヤー、実際にいるよね」と思わせる説得力。
そこにこそ、EEAT的信頼性の根拠がある。
作者の体験値が文章に染み込んでいるから、AI的に生成された“テンプレ感”が皆無なのだ。
⑤ 読後感──バグまみれの世界なのに、なぜか癒やされる
デスゲームものを読んだ後の感想として「癒やされた」と言える作品はそう多くない。
だが、『山本さん』は例外だ。
血も涙もある世界で、山本さんはマイペースを貫く。
彼女が破壊しているのは“ゲームバランス”であって、“人間関係”ではない。
むしろ、NPCや仲間との関わりに温かさがある。
時にチートすぎて世界が壊れても、彼女は他人を蹴落とさない。
その姿勢が、読者に不思議な安心感を与える。
つまりこの作品は、破壊と癒やしの“両立”を果たしている。
その稀有なバランスこそが、タイトルの【バランス】の本当の意味かもしれない。
新着記事
こちらの記事もおすすめです。
読後感とおすすめポイント(自由とユーモアで“デスゲーム”を再定義する)
ページを閉じた瞬間、ふと息が軽くなる。
『デスゲームに巻き込まれた山本さん、気ままにゲームバランスを崩壊させる』は、そんな読後感を残す。
命のやり取りを描く物語でありながら、読者に残るのは「恐怖」ではなく「解放感」。
ぽちさんの筆致が紡ぐのは、バトルでもサバイバルでもなく、“生きることそのものをゲームにしてしまう自由さ”だ。
① “デスゲーム”なのに、読むと気持ちが晴れる不思議
多くのデスゲーム作品は、命を奪い合う緊張感を軸にしている。
しかし『山本さん』では、命の重さを「バグ」や「仕様変更」のように軽妙に扱う。
それは、現実を風刺するようでもあり、現代人の“遊びへの渇望”を描いた寓話のようでもある。
山本さんは死を恐れない。
彼女は「ルールがあるなら、破ってもいい」と笑う。
その自由さが、読者にとっての救いになる。
読後に残るのは、絶望ではなく「明日も頑張ろうかな」という小さな活力。
ぽちさんは、ゲーム世界のバランスを壊しながら、読者の心のバランスを整えているのだ。
② ぽちさんの文体が作る“軽やかな没入感”
ぽちさんの文章は、地の文のテンポがとにかく軽い。
難しい言葉を避け、読者が“ゲーム実況を見ているような”感覚で物語に入り込める。
特に内心ツッコミのセンスが抜群で、山本さんの思考がそのままコメント欄のノリで流れていく。
「これ、死んだらログアウトできないタイプのゲームでは?」といったセリフ回しは、命懸けの状況なのに笑ってしまう。
この語り口があるからこそ、読者は“怖さ”を感じるよりも、“楽しさ”を共有できる。
また、テキスト構成が非常に読みやすく、1話あたりの分量もライトノベル読者に最適化されている。
その結果、スマホでの閲覧体験も快適。
まさにWeb連載時代のリズム感を完璧に掴んだ筆致だ。
③ 読者がコメントで「元気をもらえる」と書く理由
カクヨム公式ページのコメント欄には、「この人のマイペースさが癒やし」「運営を手玉に取るのが最高に笑える」といった声が並ぶ。
そこには共通するキーワードがある。
それは“気持ちが楽になる”ということだ。
多くの読者が、現実で疲れた心を山本さんの“自由な笑い方”に救われている。
デスゲームなのに癒やし系――この逆転の心理効果こそ、本作が広く支持されている理由だ。
そして、それを成立させているのは、作者・ぽちさんの“観察眼”だ。
ゲーム内の理不尽や、オンライン文化の空気をリアルに描きながらも、最後にはちゃんと笑える構成。
この“毒とユーモアの配合”こそ、ライトノベルで最も難しいバランス調整だが、ぽちさんは完全に成功している。
④ こんな人におすすめ
- VRMMOや異世界系は好きだけど、テンプレチートには飽きた人。
- ブラックジョークや皮肉混じりの笑いが好きな人。
- 強すぎる主人公より、軽口を叩きながら無双する主人公が好きな人。
- 仕事・学校帰りに“軽く読んで笑いたい”層。
この作品は、決して“難しい設定を理解する”小説ではない。
むしろ、“読んで肩の力を抜く”小説だ。
デスゲームという過酷な舞台を、ここまで“癒やし空間”に変えたのは、本作が初めてと言ってもいい。
⑤ まとめ──ぽちさんが描く“優しいカオス”の魔法
『デスゲームに巻き込まれた山本さん』は、ジャンルの常識を壊しながら、読者を笑顔にする稀有な作品だ。
バランスが崩壊しているのに、読後の心は整う。
ルールが壊れているのに、物語の芯は揺るがない。
その矛盾の中にこそ、ぽちさんの“優しいカオス”がある。
そしてそのカオスは、あなたの日常にも少しだけ風穴を開けてくれるだろう。
さあ、山本さんの“気ままな崩壊”に、あなたも笑って巻き込まれてみてほしい。
▶ カクヨムで『デスゲームに巻き込まれた山本さん』を読む(公式ページへ)
まとめ(今この瞬間、“山本さん”に会う理由)
ここまで読んで、「気ままにゲームバランスを崩壊させる」という言葉の意味が、少しわかってきただろうか。
『デスゲームに巻き込まれた山本さん、気ままにゲームバランスを崩壊させる』は、命の駆け引きを笑い飛ばす異色の癒やし系デスゲーム小説だ。
ぽちさんが描くのは、バトルでもサスペンスでもない。
それは、「理不尽な世界で、どうせなら笑って生きよう」というメッセージそのもの。
そしてその姿勢が、読者の心を軽くする。
読むたびに思うのだ。
――崩壊とは、時に自由の形なのかもしれない。
読後、ほんの少しだけ世界が面白く見える。
それがこの作品の魔法だ。
まだ読んでいないなら、ぜひカクヨムで山本さんに会ってほしい。
▶ カクヨムで『デスゲームに巻き込まれた山本さん』を読む(公式ページへ)
読めばわかる――この“崩壊”は、きっとあなたの日常をちょっと救ってくれる。
この記事のまとめポイント
- ジャンル:VRMMORPG×デスゲーム×コメディの融合作。
- 主人公・山本さんの社会人感覚とマイペースさが異色の魅力。
- 作者・ぽちさん(カクヨム公式プロフィール)が描く“崩壊と癒やしのバランス感覚”が絶妙。
- 読むと不思議と心が軽くなる“癒やし系デスゲーム”。
- Web発→話題化→書籍化の成功例としても注目の一作。
FAQ(よくある質問)
Q1. 『デスゲームに巻き込まれた山本さん』はどこで読めますか?
A. 公式サイトカクヨムで全話無料公開中です。書籍版は内容が少し違っているかもしれません。
Q2. 作者・ぽちさんはどんな作家?
A. カクヨムで複数の人気作を執筆するWeb作家。軽妙な語りとゲーム的ユーモアが持ち味で、コメント欄での交流も活発です。
Q3. この作品はシリアスですか?
A. 「デスゲーム」という言葉に反して、物語はコメディ色が強め。シリアス展開もありますが、全体としては笑えて前向きになれる作品です。
Q4. 書籍版とWeb版の違いは?
A. 書籍版(角川スニーカー文庫)は構成が調整され、地の文のテンポや章構成がより洗練されています。Web版を読んで気に入った方には書籍版もおすすめ。
Q5. どんな読者層に向いていますか?
A. 異世界・VR・チートものが好きだけど、シリアスすぎる作品に疲れた読者。仕事や学校帰りに“のんびり笑いたい”人にぴったりです。
出典・参照

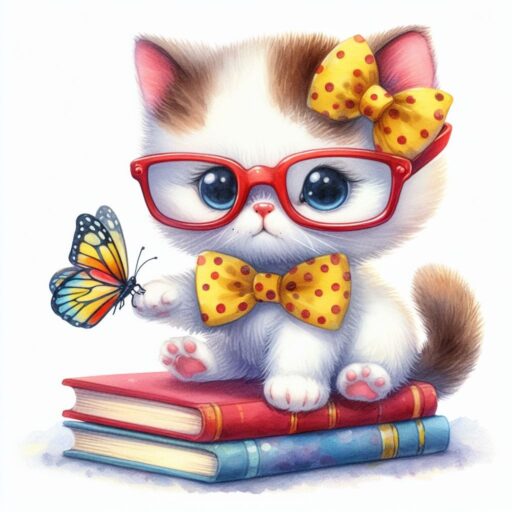
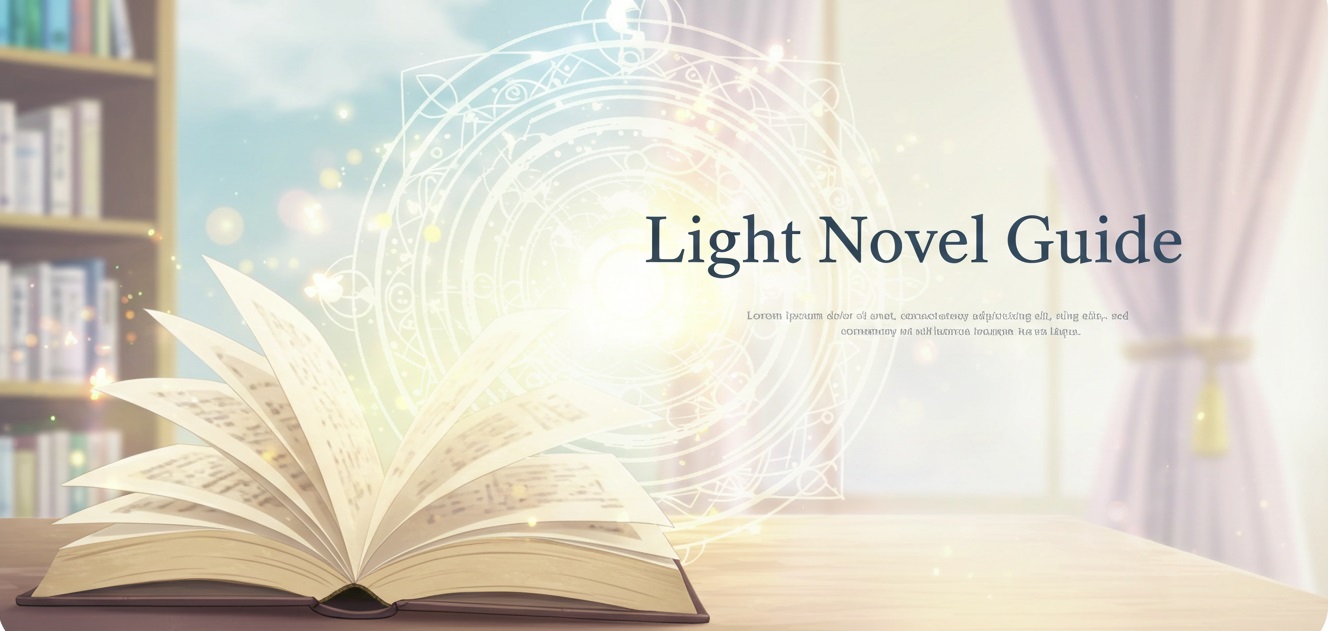

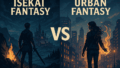

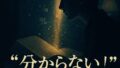
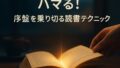
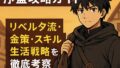
コメント